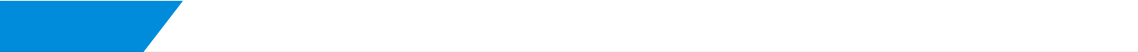TMTサイエンスワークショップ第3回が開催
TMTを用いた新しいサイエンスケースの創出を目指すワークショップシリーズ(TMT-ACCESS)の第3回ワークショップが7月15日~18日に国立天文台三鷹キャンパスにて開催されました。今回は「極限性能を引き出すための装置開発の課題とブレークスルーに向けて」をテーマとして、招待講師による講演、分野横断型のグループディスカッション、ラボツアーを4日間に渡って行いました。総勢43名の大学院生、若手研究者、スタッフに参加いただき、グループディスカッションでは事前アンケートで議論したい装置を決定した上で、TMTの次世代装置の計画を議論しました。今回は、国立天文台の尾崎 忍夫氏、京都大学の山本 広大氏、東京大学の上塚 貴史氏、ABC/国立天文台の小谷 隆行氏の4名が講師を務め、実践的な装置開発研究についてお話しいただきました。また、初日には、JWSTによる最新の研究を紹介し、TMTの将来装置に求められる機能・性能の議論につなげることを目的としたセッションが開催されました。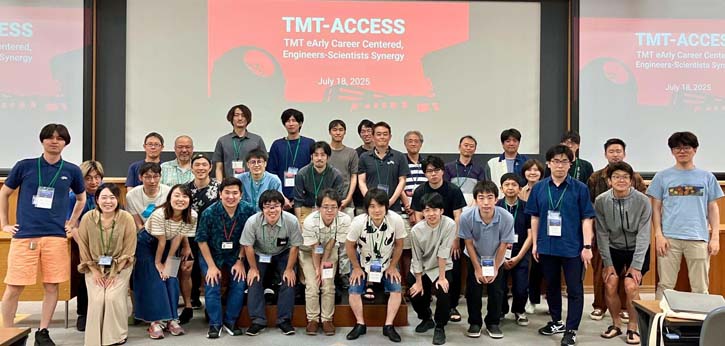
ワークショップの立案と運営は、国立天文台内外の若手の天文学者と技術者の12名からなる世話人グループが行いました。以下では、その内の3名からのコメントを紹介します。
瀧本幸司(JAXA宇宙科学研究所;世話人)
私はスペース観測機器のユーザーかつデベロッパーなので、地上観測にはあまり馴染みがないのですが、当時(第2回)の世話人の方から、「地上大型望遠鏡とスペース望遠鏡の両方を相補的かつ戦略的に活用することが不可欠であり、両者は切っても切り離せない関係だ!装置開発を専門とする人が少ないから来て!」とお誘いをいただき、第2回ワークショップから参加してみました。予告通り、装置開発をやっている人は殆どいなかったので、無い知恵を絞って装置性能の提案をした記憶があります。第2回ワークショップが終わり、(勉強にもなったし、雰囲気も良くて楽しかったなぁ。来年度もまた参加…)と思っていた約半年後、今度は「世話人をやらないか!」とお誘いをいただきました。その時点では第3回のテーマは未定のようでしたが、「より装置のウェイトを置いたものにできれば良いなと思っています!」との事だったので、二つ返事で承諾しました※。
第3回ワークショップは、テーマを“極限性能を引き出すための装置開発の課題とブレークスルーに向けて”とした甲斐もあり、装置開発者がグンと増えた印象を受けました。それに伴い、(良くも悪くも)現実的な将来装置の検討が出来たのではと思います。一番の収穫は、『サイエンティストとエンジニアが、どうコミュニケーションを取ると良いか』が、ぼんやりと分かった事でした。私は工学脳寄り(+勉強不足)なので、理学メインの方がやりたいサイエンスを力説してくれても、いまいち理解できず、途中から宇宙人と話している気分でした。ただ、後半になって、(もっと定量的に、数字で議論すれば、会話できそう…)と思い、提案・実行してみると、「このサイエンスには波長分解能が30万くらい必要です。」「500nmより短波長側はAOの効きが悪くなりそう。」といった具合に議論を進めることができました。一方で、(自身がサイエンスケースをある程度把握していれば、コミュニケーションで躓くことも無かったな…)と反省しており、『デベロッパーはユーザーと同じ水準でサイエンスケースを理解する必要があり、逆(装置開発)もまた然り』という課題が浮き彫りになったように感じました。TMT-ACCESSでは今後さらに深い議論が必要になると思いますので、理学と工学の二刀流を目指したいですね。
※実のところ、打上げ目前の観測機器の取りまとめや家庭環境の変化によって、世話人らしい裏方仕事が殆ど出来ず、他の世話人メンバーには大変ご迷惑をおかけしました。
鈴木竜二(TMTプロジェクト;世話人)
TMT-ACCESSの世話人に参加したきっかけは、確か世話人の鵜山さんから声をかけていただいたことだったと記憶しています。世話人の中での私の役割は、「TMTプロジェクト側からの世話人」、「装置開発の立場からのインプットを出せる人」と勝手に認識していました。私は現在TMT第一期観測装置IRISの開発に携わっています。長年TMTプロジェクトにいて、TMTにおいてどの様にサイエンスと観測装置の設計が結びついているのかを見てきたため、この点のインプットもワークショップへ貢献できればと思っていました。
今回のワークショップの感想ですが、まずは準備のことから。今回は、過去2回の開催の経験を元に、「より具体的な次世代望遠鏡を見据えた装置」の提案を目指しました。本ワークショップは毎回新しいテーマで行っていますが、限られた時間で意味のある成果を出せるようにするために、メインとなるグループディスカッションの制度設計がとても難しいです。何度も議論をして事前準備をし、無事開催にこぎつけた世話人の皆さん、特に議論をリードしてくださった米田さん、お疲れ様でした。当日は、頭を常時フル回転させ続けた3日間でした。サイエンスの理解、機能/性能要求への定量化、既存/計画中の観測装置との比較、観測装置のアーキテクチャの考察、開発要素の同定と開発プランの考察。普段はもっと時間をかけて行う作業のエッセンスを3日で駆け抜けるのですから稀有な体験です。また観測、理論、装置開発の人が一同に会してグループディスカッションをするという意味でも、他ではなかなか得られない体験だと思います。最近脳に刺激が足りてない方、視野を広げてみたい方、他の分野にも知り合いを作りたい方、観測装置開発に興味のある方、次回のワークショップへの参加、特に世話人としての参加、お待ちしています。
最後に、今回も素晴らしい観測装置、サイエンスの提案がありました。ワークショップでの成果をISDTやR&Dなど具体的なアクションに繋げるべく、世話人及びプロジェクトのメンバーとして模索していきます。
小野里宏樹(国立天文台;世話人)
ワークショップシリーズとして開催されているTMT-ACCESSも今回で3回目となりました。第1回はTMTを用いて行いたいサイエンスを、第2回はサイエンスを実現させるための「夢の装置」を議論することが主眼にありました。今回は「極限性能を引き出すための装置開発の課題とブレークスルーに向けて」をテーマとし、前回の夢の装置からより現実的に開発可能なスペックの装置を考え、そのスペックで実現できるサイエンスについて議論しました。観測装置について踏み込んだ議論ができるように装置開発者の参加を積極的に募り、その甲斐もあり各グループに複数人の装置開発者を交えて議論を行うことができました。
今回、装置開発者の方とグループディスカッションを行うことができて、観測装置の制限についても定量的に議論する機会を得ることができました。普段サイエンスを考える際には観測の準備でもデータの解析でももちろん定量的に考えているのですが、観測装置を考える際には意外に定量的に考えることができていないことを実感しました。例えば視野を広げるためには検出器が多く必要になるので費用が嵩み、赤外線検出器では冷却が大変そうなど何となくは思っていました。しかし、具体的に議論するとTMTのスペックを最大限活かすためには検出器が数千個必要になったり、補償光学のためのレーザーも数百本打つ必要があったりとより厳しい現実を思い知ることとなりました。最終的には、比較的現実的な開発要素で実現できる視野・空間分解能と挑戦的な開発要素により実現できそうなサイエンスへと落とし込むことができ、ワークショップの目的でもあったサイエンスと装置開発の間のせめぎ合いを体感することができました。
世話人としては開催地ということもあり事務的なことを中心に担当しました。そのため、すばる室の事務の方とさまざまなやり取りを行い、助けていただくことが多々ありました。ここで改めて感謝申し上げます。